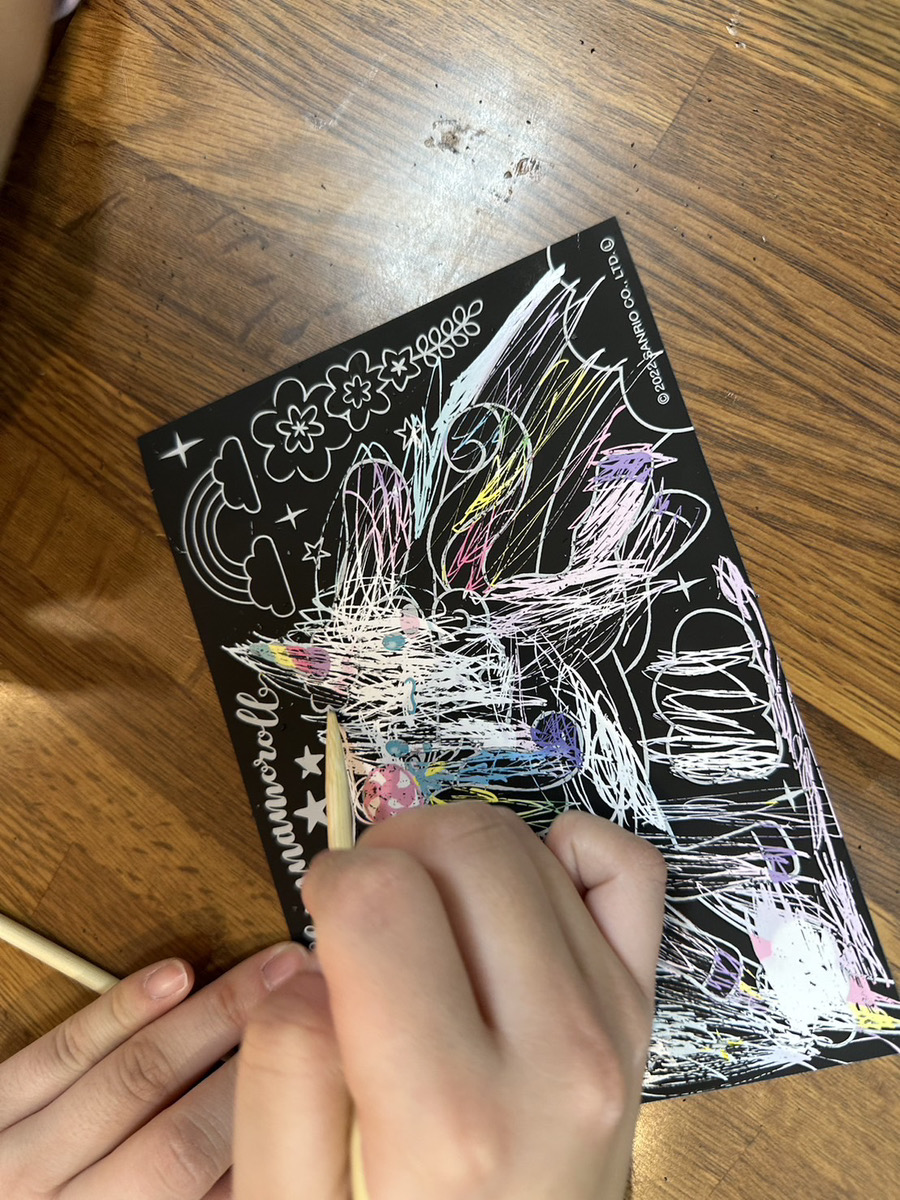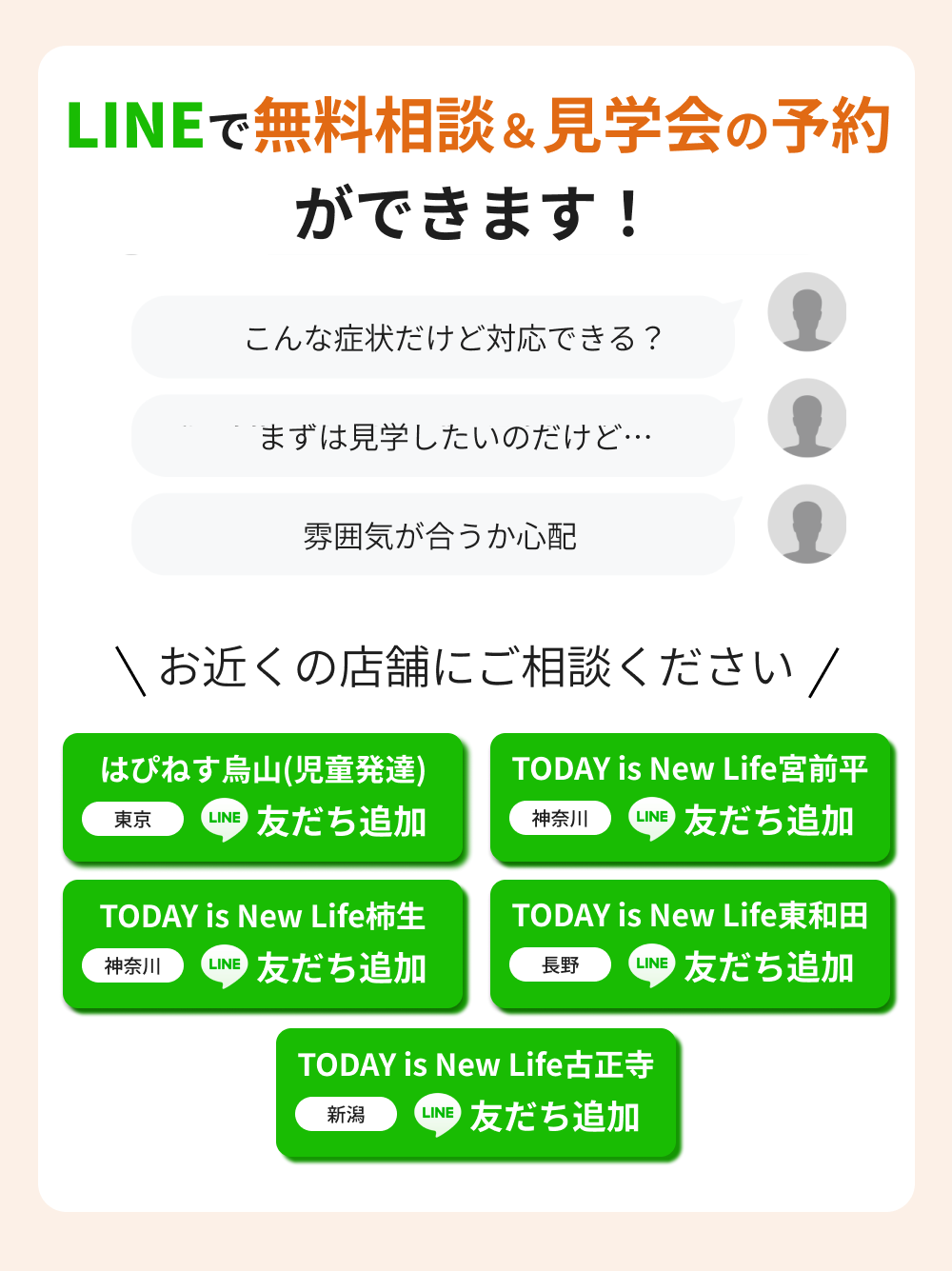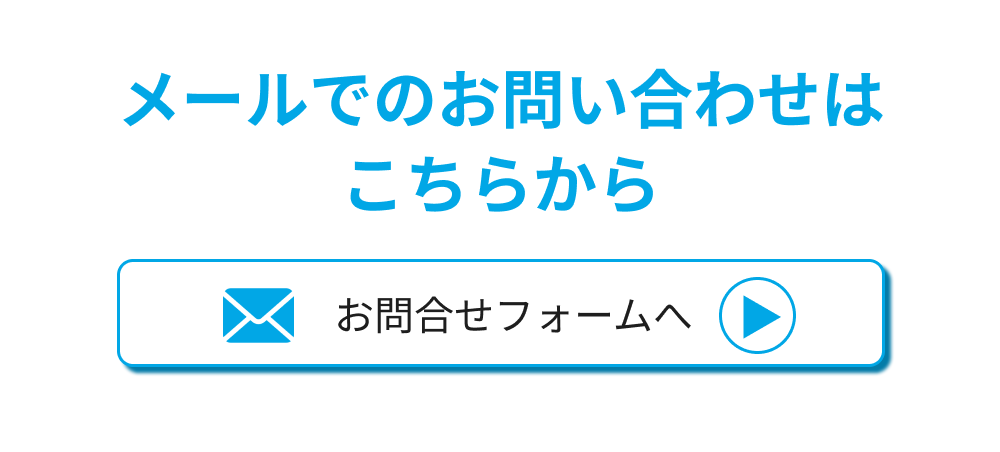施設概要

<住所>
〒157-0062
東京都世田谷区南烏山6-33-33 ウィスタリアハウス2-1F
<アクセス>
京王線「千歳烏山駅」下車北口を出て徒歩3分
旧甲州街道を過ぎ、右手に「まいばすけっと」が見え、そのまま少し歩くと左手がはぴねすの事業所になります。
<ご利用時間について>
|
|
平日 |
土曜日・日曜日 |
学校休業日 |
|
|
長期休暇など |
金曜日* |
|||
|
営業時間 |
14:30~18:00 |
9:00~16:00 |
9:00~16:00 |
12:00~18:00 |
|
サービス |
15:00~18:00 |
10:00~16:00 |
10:00~16:00 |
12:00~18:00 |
*学校休業日(長期休暇中・祝日など)にあたる金曜日が対象となります。
※年末年始(12/30~1/3)のみのお休みとなります。